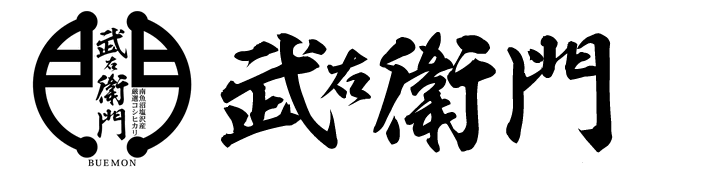2020年度 お米づくりの1年を紹介!making rice
2020年4月 雪解けのころ
今年の米づくりはコロナ禍の緊張化だけでなく、新潟県の冬場の異常気象からのスタートになります。
コロナの話題で埋め尽くされた昨今ですが、この冬の新潟県は異常ともいえるくらいの小雪でした。
下の写真は4月の同じころに撮影した写真の比較です。
ご覧のとおり、4月なのに全く雪がありません・・・ってこの感覚は雪国の人だけでしたね^-^


写真左:2019年の4月の風景 写真右:2020年の4月の風景
普通の生活を送っている分には雪は移動の邪魔になるやっかいものなのですが、
雪国の生活は様々なところで雪を活かしています。
わかりやすい話で言えば、スキー場周辺リゾートの観光収入。
土建屋さんは消雪工事や除雪作業。建設会社さんだけでなく、建築屋さん、造園屋さんなど
も携わっています。
そして我々農家にとっても雪はとても重要な役割を果たしています。
野菜農家さんですと、雪室貯蔵野菜、(雪下人参など)。
雪の中で保管する事でエグみが消え、糖分が増して美味しくなるそうです。
そして、お米づくりでは『雪解け水』です。
魚沼地方の山々は冬場に大量の雪が降り、それは夏場ごろまで徐々に溶け出しながらも
消えずに残っています。この雪からとけ出した水『雪解け水』が田んぼの水に使われるのです。
雪解け水が田んぼにもたらしてくれる恩恵は2つあると思っています。
ひとつは山のミネラルです。
通常の田んぼですと川から引いた水が使われますが、私たちの田んぼに引かれる雪解け水は
山の大地から吸収したミネラルを届けてくれます。
そして、もう一つの恩恵が『田んぼの水温(昼夜の寒暖差)』です。
魚沼産コシヒカリの美味しさの秘密として昼夜の寒暖差が激しいため、
お米は自身を守るために糖分を稲にぎゅっと閉じこめるので、食味が良いといわれています。
この寒暖差を生じさせるのに、夏場でも冷たい山の雪解け水は役にたっています。
・・・とウンチクを語っていたら、まだ米づくりの紹介をする前からページの半分以上を
割いてしましましたね・・・^-^
とにかく!
今年の米づくりは雪解け水が少ない事を予想して計画を立てないといけません。
お米農家の知識と経験が試される一年になりそうです。
2020年4月 中旬 種子洗浄から苗箱づくり

本来は雪の処理を始めるところからのスタートのはずが、今年はその作業がなかったため、
いつもより遅めの米づくりのスタートになりました。
稲籾から雑菌を取り除き、元気な苗を育てる種子洗浄を行ったのち、
(今年は写真ありません…ので右の過去写真にて代用)
2020年4月18日 苗箱づくり
発芽を促すために苗箱に敷き詰める作業です。専用の設備で苗箱に土と肥料と種籾と水を均等に分けていきます。(写真下4枚)




(写真右下)直接関係はない写真ですが、現場で必要な資材はその場で手作りが武右衛門流!
苗箱づくりは私たち女衆のチームワークが活きる作業ですね!
2020年4月21日 プール育苗
例年ですと育苗棚で芽出しした後、ビニールハウスにて育苗を行うのですが、 今年は温暖で、天気も安定していたため、プール育苗に切り替えました。育苗棚で30~32度の温度で2日間、稲籾は1cmほどに発芽します。 芽出しした稲をビニールシートで作ったプールに並べていき、シートをかぶせて苗の生育させます。(写真下)




写真左:2020年4月21日プール育苗開始 写真右:2020年5月2日の風景・苗は8cmほどに成長
2020年4月25日 田んぼの耕耘

田んぼを耕し、田んぼ全体の土の状態を均一にする作業です。
写真は武右衛門で一番見晴らしの良いインスタ映えする田んぼで撮影しました!
2020年5月5日 肥料

耕運機に肥料を載せて、耕耘した田んぼの土と肥料を混ぜていきます。